公務員試験の「憲法」では、判例の勉強が欠かせません。特に日本国憲法第19条に定められている思想良心の自由は、覚えないといけない判例が数多くあります。
この記事では、公務員試験用に思想良心の自由の重要な判例を紹介します。
思想良心の自由とは
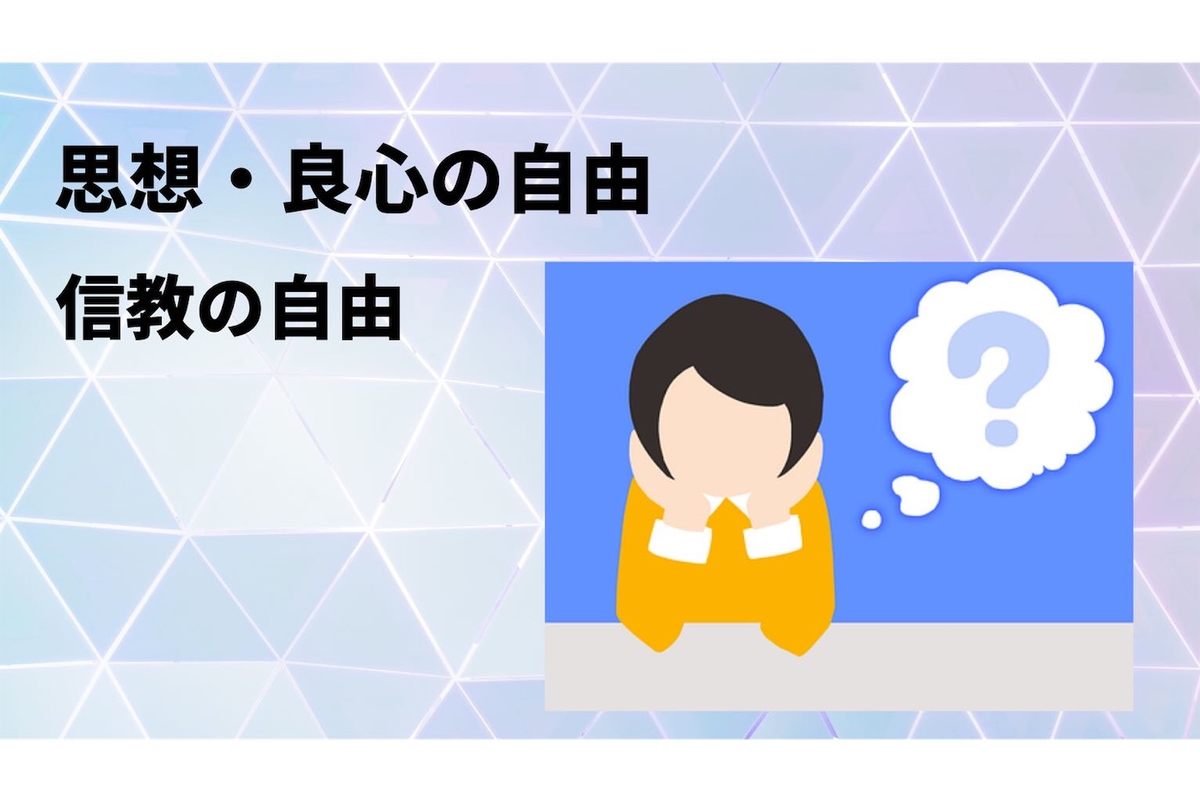
思想良心の自由とは、特定の思想を抱くことに対する自由のことです。皆さんも選挙権を持ったことで、自分の意思で好きな政党に投票できます。
また政治のやり方に納得がいかなければ、本やSNSで自由に文句も言えます。仮に文句を言ったとしても、国から弾圧されることもありません。
ここでは判例を説明する前に、思想良心の自由の概要や歴史を解説します。
思想に関する歴史
今では思想良心の自由を皆が有しているものの、大日本帝国憲法時代は制限されていました。これまでの歴史の中で、特定の思想を抱いていた人々が弾圧された事件は以下のとおりです。
- 大逆事件
- 滝川事件
- 天皇機関説事件など
自分の意見を主張した者は捕らえられ、中には「死刑」となった人もいました。つまり国家が国民をコントロールしていた時代ともいえます。
このような社会をなくすためにも、思想良心の自由が明確に憲法で示されました。
思想良心の自由は干渉されない
思想良心の自由は「絶対的」とされ、内心に留まる限りは誰にも干渉されることがありません。さらに国家に対して、内心を無理に吐かせる行為を禁じています。
かつて鎖国をしていた徳川家光時代は、キリスト教を禁じるべく国民に絵踏を強制しました。このような行為は、現代社会では禁じられたわけです。
思想良心の自由の判例
はじめに、思想及び良心の自由に限定して判例を取り上げてみます。ここで習う判例は、いずれも重要なものばかりです。今回は4つに限定して紹介しましょう。
- 謝罪広告事件
- 三菱樹脂事件
- 麹町中学校内申書事件
- 南九州税理士会政治献金事件
紹介し切れなかった判例は、タイミングを見て別の記事で取り上げられればと思います。
謝罪広告事件
謝罪広告事件は、衆院選に出馬した候補者同士の争いが発端となった事件です。候補者Xは、別の候補者Yを「汚職している」と虚偽の情報を広めました。
YはXに対し、名誉回復のため謝罪広告を公表するよう訴えを起こします。結果的に下級裁判所は、Xに謝罪する義務があると判断しました。
Xは、謝罪を義務付けることが憲法19条に違反すると反論します。
この件に最高裁は、に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度単であれば、思想・良心の自由は侵害しないと判断しました。
三菱樹脂事件
三菱樹脂事件とは、三菱樹脂株式会社の採用試験の合格者の一人が、学生運動の参加に関して虚偽の申告をしたとして採用を拒否された事件です。
企業が特定の思想に基づいて採用拒否することは、憲法に違反するのではと争われました。
最高裁判例は「企業が持つ雇用の自由」も視野に入れます。最終的には、企業が労働者の思想や信条を調査して採用か否かを判断しても問題ないと結論を出しました。
麹町中学校内申書事件
政治的活動(全共闘を名乗るビラ配り)をしていた生徒が、内申書にその運動の内容を書かれて受験した高校を全て落とされてしまいました。
なかなかショックな出来事に対し、生徒側は国に賠償請求を求めます。(国家賠償請求訴訟)
最高裁は学校側が思想や信条をそのまま書いたわけではないことに目を向け、内申書は思想良心を侵害しないと判断しました。
南九州税理士会政治献金事件
政治献金事件というと「八幡製鉄株式会社政治献金事件」を思い出す方もいるでしょう。ただ、南九州税理士会政治献金事件は結論が大きく異なります。
税理士会は基本強制加入団体であり、脱退の自由が認められていません。加えて、最高裁は税理士会の政治献金が目的の範囲外の行為と判断しました。
したがって、寄付行為を義務付ける本件は違法とされています。八幡製鉄株式会社の事件については、以下の記事でまとめているので参考にしてください。
信教の自由とは
信教の自由とは、日本国憲法第20条に規定されている宗教上の信仰などを保障する権利です。こちらは信仰の自由のみならず、祝典や儀式の参加を強制されない自由も含みます。
また信教の自由において、しっかりと押さえておく必要があるのが政教分離の原則です。宗教団体は国から特権を受けてはならず、国主体の宗教的教育も認められません。
信教の自由の判例
次に『信教の自由』に関する判例をまとめていきましょう。
ここで紹介するのは以下の4つです。
- 加持祈祷事件
- 津地鎮祭事件
- 愛媛玉串料訴訟
- 箕面忠魂碑訴訟
結論部分さえ押さえればいいため、事件の経緯を捉えてください。
加持祈祷事件
この事件は細かく調べるとかなり残虐です。ここでは経緯と結果だけを書いていきますね。
精神的異常の状態が見られた少女に対し、治療を依頼されていた尼僧は加持祈祷を行います。しかし実態は単なる暴行同然でした。
結果的に被害者は死亡し、最高裁は尼僧の行為が反社会的であるとして信教の自由を逸脱したものと判断しました。
津地鎮祭事件
三重県の津市が市体育館を設置する際に地鎮祭を行って7633円のお金を支出したのが問題視された事件です。
政教分離原則に違反するのではと住民訴訟が提起されましたが、最高裁は以下のような結論を出します。
- 本件起工式は宗教とかかわりを持つのは否定できない。
- しかし、社会の一般的慣習であって宗教活動にはあたらない
愛媛玉串料訴訟
これは愛媛県が靖国神社に対してお祭りに使う玉串料を7万6000円ほど支給した事件です。
津地鎮祭事件と似ているような気もしますが、この事件では愛媛県の行為が違法と判断されました。
起工式とは異なり、神社の玉串料奉納が「社会的儀礼といえない」ことが要因と挙げられています。
箕面忠魂碑訴訟
非宗教団体である遺族会が慰霊祭を忠魂碑前で行うにあたり、市長や教育長がその準備をするために公費を使いました。
司法は遺族会が
- 宗教を目的とした団体ではない
- 小学校校舎の建て替えがもう一つの目的にあった
ことを考慮して宗教的活動にあたらないとしました。
他にも
- 殉職自衛官合祀事件
- 大阪地蔵像違憲訴訟
- 空知太神社訴訟
といった公的機関と宗教の問題がありますが、どれも公的機関側に違法が見られないと判断しています。
まとめ
今回、記事で取り上げた内容は「思想良心の自由」「信教の自由」です。
ここで紹介した判例は、公務員試験で必ず覚えておかないといけません。公務員試験のレベルであれば、まずは結論部分(違憲かどうか)から先に押さえてください。
ただし結論部分を暗記するだけでは、いざ出題されたときに忘れてしまう恐れもあります。問題集2周目のあたりで、各事件のざっくりとした内容も見ておくとよいでしょう。