行政活動は法律に則る必要がありますが、束縛があまりにも厳しいわけではありません。行政裁量といって、ある程度は行政自らが自由に判断できます。
この記事では、要件裁量と効果裁量の違いと行政裁量に関連する判例を解説します。
公務員試験でも頻出度はそれなりに高い分野です。この記事を参考に、どういう問題が出題されやすいかを捉えましょう。
行政裁量とは
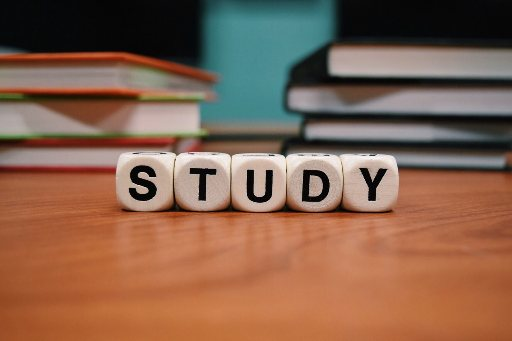
裁量とは、その人自身の判断で処理をすることです。
行政裁量に当てはめて考えれば、行政の判断で処理をする状態を指します。
行政は基本的に法律のルールに沿って活動します。しかし、行政の仕事内容は多種多様で膨大の事務をこなさなければなりません。
いちいち法律的に問題がないかを調査していたら、業務が進まなくなるでしょう。住民の利便性にも影響が出るので、原則として行政は自由に判断できます。
行政裁量には、大きく分けて要件裁量と効果裁量があります。
要件裁量と効果裁量の違い

要件裁量と効果裁量の違いは、便宜裁量と法規裁量の区別を付ける基準にあります。それぞれの区別の付け方がこちらです。
- 要件裁量:法律の要件に当てはまるか
- 効果裁量:効果をどう与えるか
細かい内容について詳しく解説しましょう。
要件裁量
要件裁量とは、法律の要件の当てはめ段階における裁量と定義されます。この裁量が認められる条件の例は、政治的判断が必要な場合や専門的な知見を要する場合などです。
「マクリーン事件」は、政治的判断が必要であるゆえに要件裁量を認める判例を出しました。
在留外国人の在留期間に関して「出入国管理令の規定」に沿うものの、判断は法務大臣の裁量に任せられています。
その裁量が常識的に考えて妥当性を欠いていなければ、違法にはならないと最高裁は最終的に判断したわけです。
効果裁量
効果裁量は「行政がどのような処分を用いるか」といった手段や方法に関する裁量です。法律の要件はすでに満たされており、その効果が適用されるか否かを決めるときの裁量と考えるとよいでしょう。
国家公務員の懲戒処分の判例が、最も分かりやすいと思います。
例えば、国家公務員が失態を起こして問題となったとします。この時、国家公務員法の規定に従って次の処分が可能です。
- 戒告処分(口頭注意)
- 減給処分(給料を下げる)
- 懲戒解雇(クビ)
効果裁量により、どの処分を選ぶかという決定権は行政に与えられます。
効果裁量も要件裁量と同じく、裁量の範囲を逸脱または濫用が見られたときに司法の判断も適用されます。
ちなみに、行政裁量には時の裁量という概念も欠かせません。
行政が裁量権を発揮するタイミングもまた独自で判断できるといった裁量です。
過去にも出題されているため、タイミングにも裁量権が与えられることは覚えた方がいいでしょう。
法規裁量と便宜裁量
行政に裁量が認められたら、今度はどこまでの行為に裁量があるかを司法審査の観点から判断します。
これを裁量行為と呼び、大きく法規裁量と便宜裁量に分けられます。これらも公務員試験では、問われる可能性の高いジャンルです。しっかりと区別して覚えてください。
法規裁量(覊束裁量)
法規裁量(覊束裁量)とは、法律の客観的判断が存在する行為のことです。羈束は「きそく」と読むので、読み方も併せて覚えておくとよいでしょう。
法律があらかじめ裁量行為の基準を設けており、たとえ定め方が不明瞭でも司法審査の対象となります。
便宜裁量(自由裁量)
便宜裁量(自由裁量)とは、行政庁の政策的判断を尊重したほうが望ましい行為のことです。こちらは法律に基準がなく、行政の権限に委ねられています。
そのため便宜裁量の場合は、原則として司法審査には服しません。ただし「裁量権の範囲の逸脱または濫用があった」場合には例外的に司法審査の対象となります。
なお行政事件訴訟法第30条にも、裁量権の範囲を超え濫用のあった裁量処分は裁判所が取り消せる旨を定めています。こちらも便宜裁量に基づく規定です。
行政裁量と判例
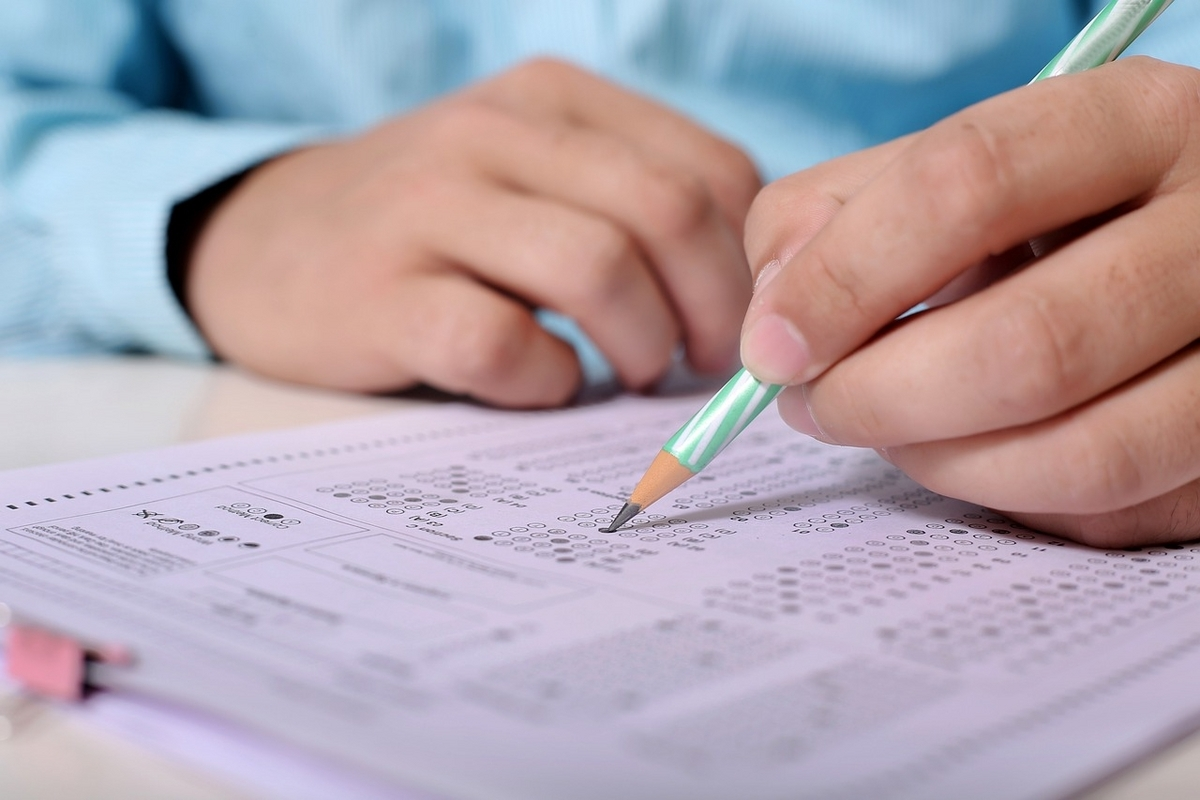
行政裁量の範囲は、判例の内容も勉強しなければなりません。ここではよく出題される判例を簡潔にまとめます。
土地収用法の判例
一般国道に面したところでお店を構えていた事業者が、『高架道路』の設置のために土地を一部収用された事件です。
事業者は土地を一部収用されて高架道路が建設され、最終的には廃業に追い込まれてしまいます。事業者は損失補償を求め、国に対して訴訟を提起しました。
最高裁は「この土地収用法における補償金は客観的に認定されるべきであり、土地収用委員会に裁量権はない」と判断します。
加えて、次の補償をすべきだと結論を下しました。
- 事業者に対する正当な補償
- 年5分にかかる金利
このような行政行為は、国民の生活にも大きな影響を及ぼします。その意味では、最高裁の判例も正しいと認識せざるを得ないでしょう。
教科書検定と国家賠償訴訟
家永教科書裁判は、ギネス認定されるほど長期間にわたった民事裁判として知られています。
こちらの事件では「教科書検定は行政が書籍の内容をあらかじめチェックする「検閲」にあたるのでは?」と争われました。
なお、検閲とは行政権が書籍や新聞などの表現内容を強制的に調べることです。日本国憲法下では、行政権がこのような権力を行使するのを禁止しています。
教科書検定も確かに書籍の内容をチェックする行為ですが、裁判所は検閲に当たらないとしました。
教育において不適切な教科書が使われるのを防ぐ方が重要であるためです。ただし、検定内容に裁量権の逸脱がないことを条件としています。
伊方原発訴訟
こちらは「原発」の建設について争われた事例です。原発の新設に反対した住民が訴訟を起こしました。
原発の基準は専門委員会の科学的な見解を根拠とすべきでは?と問題視されます。
一応、裁判所は専門委員会の知識も参考にしながらも、内閣総理大臣の裁量は認められるとして住民側が敗訴しました。なお科学技術水準については、事件のあった当初ではなく「現在」に照らして考える点もポイントです。
しかし、2011年東日本大審災を皮切りに再度訴訟が起こされ、現在も係争中(争いの途中)とされています。
児童遊園設置
これは山形県余目町の事例ですね。余目町にトルコ風呂という風俗店が建設されるとし、住民の反対運動が起こります。そこで住民は県知事に200m以内のところへ児童遊園を設置するよう申請を出しました。
風俗店は児童施設から200m以内のところでは運営できないこととなっています。
県知事はその申請を受理して児童遊園を設置し、風俗営業側の怒りを招いて訴訟へ発展しました。司法の判断は行政の児童遊園を設置する行為は裁量の範囲を逸脱しているとし、違法と判断します。
剣道受講拒否事件
最後に剣道受講拒否事件を紹介しましょう。
これはある宗教上の理由により、剣道を受講できない高校生がその授業を休んでいました。
学校側は何の代替措置もとらず、剣道を受講しなかったとしてその生徒に「留年処分及び退学処分」を下します。この措置に問題あるとして訴訟が起こされました。
最高裁は以下の条件を理由に学校が留年処分や退学処分を下したのは違法だと判断しました。
- 剣道が進学に必ず必要だと言い切れないこと
- 代替措置は普通に行えたはず
これらの判例は内容もしっかりと押さえておきましょう。
判例問題を解くコツ
行政法に限った話ではありませんが、判例の勉強は特に難しいと感じるかもしれません。そのため判例の結論部分を中心に、上手く分類して覚えるのをおすすめします。
行政裁量でいえば、次の2種類に分けるといいでしょう。
- 裁量が認められる事例
- 認められなかった事例
このようにするだけでも、ある程度は整理できます。
さらに、判例法において以下のように100%断言する選択肢は間違いである場合が多いです。
- 全く許容できない
- 〜する余地はない
あくまで「多い」なので一概にはいえませんが、判例は「〜しない限り」といった例外がある程度は用意されています。
選択肢が難しくて悩んだ場合は、断言しているものを積極的に取り除くのがいいかもしれません。どうしても覚え切れなかったときの最終手段と捉えてください。