大学へ子どもを通わせている方の中には、第二種奨学金の利息を借りている方もいるでしょう。
ただし、第一種とは異なり利息の部分も併せて返済しなければなりません。したがって、返済額も高くなる点が特徴です。
なお、以前に奨学金の記事を書いてみました。奨学金の制度そのものを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
今回は第二種奨学金に焦点を当て、利息の計算方法と返済額についてまとめます。
シミュレーションを使えば金額はわかりますが、ここでは具体的な仕組みを紹介しましょう。
※アフィリエイト広告を貼っている記事
第二種奨学金とは?

まずは、『第二種奨学金』とは何かを説明します。
奨学金には種類が大きく分けて2つありました。
- 第一種奨学金
- 第二種奨学金
両者の違いは、利息の有無にあります。
第二種奨学金は、利息を含めて返済額を計算するタイプです。返す金額は第一種奨学金と比べ、利息分が多くなります。
そのため、成績優良者が優先して一種の奨学金を借りられるわけです。
では、返済額が大きくなるとはいっても、具体的にどの程度異なるのでしょうか?計算方法について解説してみましょう。
ちなみに、金利の計算についてはFPの試験勉強をしてみるとスムーズに理解できます。FPの資格を取りたい方は、以下の参考書と問題集を購入してみてください。
リンク
リンク
第二種奨学金の計算方法
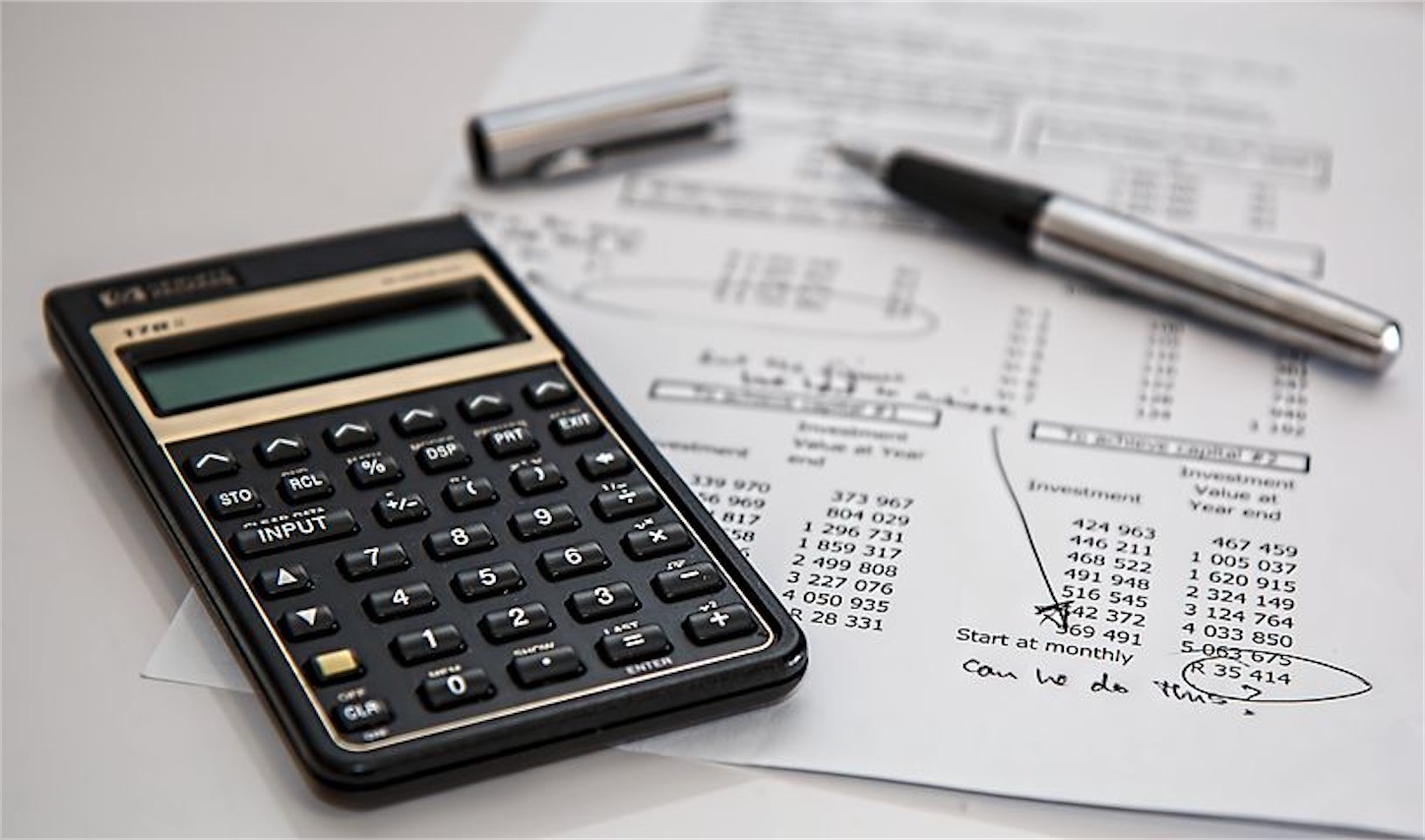
さあ、ここから難しいですよ笑金融資産の勉強をしていますが、何度も確認しながら作成していきます。
第二種奨学金の返済額を求めるうえで、
2パターンの計算方法を知らなければなりません。
- 利率固定方式
- 利率見直し方式
返済する際には、いずれかの方式を選びます。
利息=借金への対価
計算方法を説明する前に、
「利息」を少しだけ触れていきましょう。
我々が普段使うお金は、国内・国外で四六時中取引されています。金融機関からの金銭の貸し借りは、もはや日常的な行為です。
国民が消費者金融機関からお金を借りる際にも、その分の費用が発生すると考えられています。
その費用が「利息」ですね。因みに、似たような言葉として「金利」があります。主な違いは以下のとおりです。
- 利息は費用の「額」を示す
- 金利は「割合」を示す
利息は原則自由に決定されるため、貸す側の経営力や借りる側の信用によって大きく額は異なります。この利息が、返済額にも大きく響きます。
安定している利率固定方式
ここまで説明すれば、利息の意味が少しは理解できたと思います。
では、利率固定方式を紹介しましょう。
計算方法を簡単に説明すれば、「貸与終了後から返済完了まで利率を固定する方式」です。
通常、金利は市場の動きに合わせて上下します。
しかし、利率固定方式であれば第二種奨学金の利率は変わりません。そのため、安定して返済することができます。
一方で市場の金利が下がっても、奨学金には影響されない点がデメリットです。(返済額が少なくならないため)
5年で更新の利率見直し方式
一方で、利率見直し方式は「5年ごとに利率が見直される仕組み」を設けています。
利率が低くなれば返済額も元本に近づきますが、反対に高くなると返す金額も増えてしまうスタイルです。
利率は、市場金利によって左右されます。日銀の金融政策やその政策に伴う地銀の金利設定が大きなカギです。
貸与終了後の経済状況を読めるはずがないため、個人的にはギャンブルに近いのかなと思ってしまいます。
第二種奨学金の計算(実践)

最後に、第二種奨学金の利息の計算方法に関する実践的な内容に踏み込んでみましょう。例を出しながら紹介したいと思います。
大学に子どもを通わせ、なおかつ第二種奨学金を借りる方は参考にしてください。
第一種奨学金のおさらい
例えば、奨学金を月5万円借りていたとしましょう。4年制大学と想定します。
すると、学生生活で借りた総額は
5万円/月×12ヶ月×4年=240万円です。
前回の記事でも説明した通り、奨学金の返済期間は「割賦金の基礎額」を使って算定します。
日本学生支援機構の表を頼りに求めると、例示の場合は基礎額が16万円です。
つまり、返済期間は
240万円÷16万円=15年になります。(返済回数は×12ヶ月で180回)
最終的に利息を考慮しなければ、この方は月13,000円程度返済していけば良いわけです。
据置期間の計算
実は、奨学金は卒業後すぐに返済が始まるわけではありません。新社会人として基盤を作らせるため、ある程度の猶予期間が設けられています。
その猶予期間が「据置期間」です。据置期間中も利息が発生します。しかし、計算方法がやや異なります。
計算式は、以下のとおりです。
返済総額×利息
×(30日+31日+30日+31日+31日+27日)÷365日
()書きの日にちは、4月〜9月27日の据置期間の日数を指します。
第二種奨学金になると利息が絡みます。利息を2%(利率固定)で計算してみましょう。また、第一種奨学金の計算で求めた240万円の総額をそのまま使います。
240万円×2%×180日(上記の日数を全て合わせる)÷365日で23,671円と求まりました。
金額を返済期間に当てはめれば、
23,671円÷12ヶ月÷15年で月131円を追加で返済すると算出できます。
毎月にかかる返済額
毎月にかかる返済額は、計算方法も結構ややこしいです。
そもそも第二種奨学金の返済月額に関しては、
「元利均等返済方式」が用いられています。
簡単に言えば、月の返済額を一定にする制度です。3万円と定めたら、毎月絶対に3万円ずつ返済します。
初めは、金利が高めに設定されるものの、返済が続くに連れて減少するスタイルです。
そして、元利均等方式の計算方法は以下の通りになります。
「」を
「」で割る
上述の例に当てはめると、
「」を
「」で割る。
熱が出そうになる複雑な計算式ですが、表計算ソフト(Excel)を使えば簡単に求められます。
とあるセルに
=PMT(利率(%)/12,返済回数,貸与総額)と式を埋めればOKです。
すると、答えは15,444円と求まるはずです。
どうしても公式から計算したい方は、常用対数を使えば何とか出せるかもしれません。面倒なので、僕は遠慮しますが。
ここに据置期間の利息も合わせ、
15,444円+131円=15,575円と求まりました。
実際の日本学生支援機構のシミュレーションと照らし合わせてみると、返済額の数値が若干異なります。端数処理に違いが見られるためです。
どういう計算方法で端数を処理しているかは明確にされていません。とりあえずは、大体の目安として覚えておくと良いでしょう。
まとめ
今回は第二種奨学金の返済額を求める際に、利息を含めた計算方法について紹介てみました!
まずは、以下の2パターンがあると押さえましょう。
- 利率固定方式
- 利率見直し方式
そこから、実際に返済額を出す上で複雑な計算方法で算出します。表計算ソフトを用いて求めた方が簡単です。
元利均等方式は、住宅ローンの算出にも使われています。
豆知識として覚えておくといいかもしれません!