マクロ経済学の消費関数では、より長いスパンで見るライフサイクル仮説や恒常所得仮説の考え方も重要です。
今回の記事では、ライフサイクル仮説と恒常所得仮説の違いや計算方法を取り上げます。
双方の違いを押さえつつ、計算問題にも対応できるように準備することが大切です。
なお消費関数の中でも、基礎的な内容であるケインズのモデルやデューゼンベリーの内容は以下の記事で詳しくまとめています。こちらも併せて目を通すようにしてください。
※アフィリエイト広告を貼っている記事
ライフサイクル仮説とは

ライフサイクル仮説とは、消費が一生涯にわたって得られる所得に影響を受けるという考え方です。
この説を唱えたのはモディリアーニで、人々は人生の周期に依存して消費量を決めると考えました。ライフサイクル仮説の細かい内容について確認しましょう。
ライフサイクル仮説の内容
ライフサイクル仮説を捉えるうえで、欠かせないものが以下の2点です。
- 労働所得
- 資産所得
我々は、20歳あたりから65歳あたりまで、基本的には労働で収入を得ます。加えて、所有していた資産(不動産や株など)により稼ぎを得る方も一定数いるはずです。
今は何も持っていなくとも、親族からの相続で土地や建物といった資産が譲渡されるかもしれません。このように、将来得られる所得をベースに考え、いくら消費するかを計算します。
ライフサイクル仮説の計算式
続いて、ライフサイクル仮説の計算式を見てみましょう。まずは以下の式を見てください。
=
複雑そうに感じると思いますが、理屈が分かれば式を作るのは難しくありません。
ライフサイクル仮説では労働所得をY、資産所得をWで考えます。
式にあるaとbは、限界消費性向を指しています。限界消費性向とは、所得からそれぞれどのくらい消費に回すかを捉えた数値です。
C(消費)の計算式を作ると、次のようになります。
C=aY+bW
要するにaYが労働所得からの消費、bWが資産所得からの消費で、これらを合わせると消費全体が分かる計算式です。
そして最初に青文字で示した式は、平均消費性向を示しています。平均消費性向とは、可処分所得に占める消費の割合のことです。
要するに「C=aY+bW」の式に対して、「Y」を割り算したのが
=
となります。
このような式を作れば、ライフサイクルを通じてどのくらい消費するかを計算できます。
計算問題の例題は、後述しましょう。
恒常所得仮説とは

恒常所得仮説はフリードマンが唱えた説であり、人々の消費が恒常所得に依存するという考え方です。
こちらもマクロ経済学で問われやすいため、計算方法も踏まえて押さえましょう。
恒常所得と変動所得
フリードマンは、人々の得られる所得を恒常所得と変動所得に分けました。
恒常所得は、安定して得られる所得を指します。主な例が月の給料です。
一方で、変動所得は景気等に左右される一時的な所得を表しています。ボーナスがその一例です。
要するにフリードマンは、安定して得られる給料に人々は依存し、景気や運に左右される収益には大きな影響は受けないと考えました。
恒常所得仮説の計算式
恒常所得は、よくと表記されます。
pは、単純に恒常所得の印と考えてもらえれば問題ありません(僕も意味は分からないです)。tは時期を指します。
恒常所得にかかる消費の割合をaと置くと、計算式は以下のようになります。
=
フリードマンの考えを知っていれば、少なくとも消費と恒常所得がイコールで結びつくメカニズムは理解できるでしょう。
ライフサイクル仮説・恒常所得仮説の違い

ライフサイクル仮説と恒常所得仮説の違いは、消費がどの所得に依存するかです。
ライフサイクル仮説は、一生涯で得られる全ての所得が消費に影響を与えると考えます。そのため、たまたま手に入れた資産も全て対象に含みます。
一方で、恒常所得仮説は安定して得られる所得しか考慮しません。
棚からぼた餅で手に入れた資産は、消費に影響を与えないとする考え方です。
現実的に考えれば、フリードマンの恒常所得仮説の方が理に適っているかもしれません。
しかし、「パチンコで勝ったらゴルフクラブを買おう」などと、変動所得を頼りにする人もいるはずです。
あくまでマクロ経済学として考えたとき、どちらが正しいかは断言できません。個人的には、国民性が大きく影響すると思います。
日本の場合は勤勉なイメージが強いため、恒常所得仮説が当てはまるような気はします。イメージを掴めれば、式の示す意味も汲み取れるようになるでしょう。
公務員試験を受験される方の中には、転職組も少なくないと思います。
仕事を探すのであれば、王道である「株式会社リクルート」を押さえてください。
「転職Shop」では、既卒や第二新卒、フリーターを中心に正社員求人を紹介しています。
各仮説の計算方法と例題
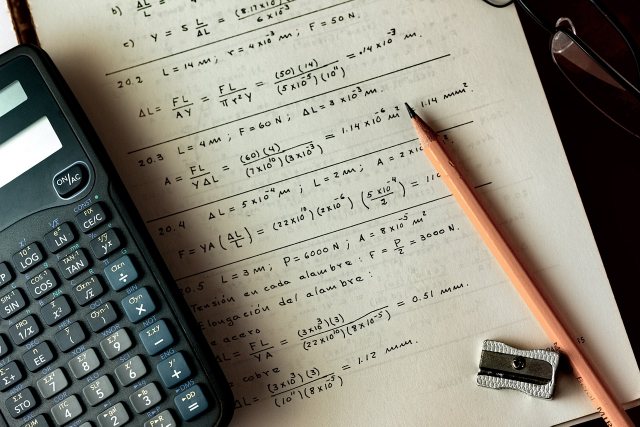
最後に、練習問題を2つ用意しました。ライフサイクル仮説と恒常所得仮説の計算問題を解いてみてください。
問題文をよく読み、式に各数値を当てはめましょう。
ライフサイクル仮説の問題
まずは、ライフサイクル仮説の問題を出します。
この間は年間500万円の所得を得る。
引退期間は10年間で、その間は所得がないと考える。
親から譲り受けた資産所得が1000万円あるとき、毎年の消費額はいくらになるか?
①360 ②400 ③420
計算がややこしいため、慣れないうちは式を作るだけでも難しいかもしれません。
ここで意識してほしいポイントは、稼働所得と生涯で得られる所得を明確に分けることです。
稼働所得を求める
まずは、Aさんの稼働所得から求めます。Aさんは40年間、会社で働いて給料を貰います。
1年間で得られる年収は500万円です。この条件から、仕事している期間に貰える所得額全額を計算しましょう。
単純に40年間×500万円で「2億円」と求められます。
稼働所得を求めたら、余白にしっかりとメモを残してください。
生涯の所得額を求める
次に、Aさんが生涯で得られる所得額を計算します。
ここで注目すべきポイントが、親から1000万円の資産を譲り受けている点です。
稼働所得の2億円に加え、1000万円を合わせた金額が生涯の所得になります。
「2億円+1000万円」で生涯の所得は「2億1000万円」です。
毎年の消費額を求める
ここまで解けたら、毎年の消費額を算出します。
この方が生きる期間は、稼働期間の40年と引退期間の10年を合わせた50年です。
1年間で1円も消費せずに生活するのは不可能であるため、50年という数字を使って解きましょう。
毎年の消費額をCと置くと、生涯の消費額は「50年×C」で50Cです。
そこで「C=aY+bW」の計算式が使われます。今回は、限界消費性向はないので、aとbは無視して構いません。
50C=2億1000万。つまり、50C=21000が毎年の消費額を求める計算式です。
計算すると、420万円(③)と求められます。
恒常所得仮説の問題
恒常所得仮説に関しては、次の問題を用意しました。
t−1期までは所得400、t期からは所得500の場合、t期の貯蓄額はいくらになるか
①100 ②200 ③400
ここでは、最後に貯蓄額が問われていることに注意しつつ、問題を解いてください。
恒常所得を求める
はじめに、与えられた条件を利用して恒常所得から求めます。
t−1期までは所得が400で、t期は所得が500になります。
これらの数値をの式に代入するだけです。すると、計算式は次のように作れます。
=
計算すると恒常所得は500です。
t期の貯蓄額を求める
次に、t期の貯蓄額を求めます。しかし、問題文には「貯蓄」が示されていません。
とりあえずは、消費=
を使いましょう。
恒常所得は500と求められたため、上記の式に代入するだけです。
すると、は400と求められます。
ただし、この400はあくまで「消費」の値です。貯蓄が求めたい値であるため、間違えないよう注意してください。
t期の貯蓄を求めるには、先程求めたt期の消費とt期の所得を使います。なぜなら「所得から消費分を引いた残り」が「貯蓄」になるからです。
t期の所得は、問題文から500と分かります。貯蓄と消費の関係性を、以下のように式で示しましょう。
=
−
=
で答えは100(①)です。
2つの仮説の違いをおさらい
今回は、ライフサイクル仮説と恒常所得仮説の違いについて解説しました。
両者の大きな違いは、消費がどの所得に依存するかです。
ライフサイクル仮説は単純に生涯の所得を合わせた考え方で、恒常所得仮説は安定して得られる所得に的を絞っています。
この2つの理論は、単なる知識だけではなく計算方法もマスターしなければなりません。何度も繰り返し問題を解きながら練習をしてください。
マクロ経済学のテキストは、以下の2点がおすすめです。こちらも併せて購入すれば、実際の公務員試験でも問題なく対処できるでしょう。
